忘れ得ぬ人びと 人生一期一会(17)作家たちのささめき(下) |
||
根本 圭助昭和10年2月、東京・南千住に生まれる。第二瑞光国民学校4年生の時罹災。千葉県柏町に移る。小松崎茂に師事。主な仕事は出版物、及び特にTVキャラクターのマーチャンダイジングのイラストで幅広く活躍する。現在松戸市在住。小松崎茂作品を中心に昭和の雑誌文化を支えた挿し絵画家たちの絵を展示する「昭和ロマン館」館長。
|
||
「おーい、時間あるか?」宗薫先生に電話でよく呼び出された。昭和30年代初めの頃である。当時柏駅の近くには喫茶店もろくになく、駅通りから一寸横町へ入った所の『ボン』という喫茶店でよく時間を潰した。 前回に記したように、宗薫先生は、私が東葛飾高校の2年生になった新学期に、英語の教師として母校に赴任して来た。これも前に書いたが、時をほぼ同じくして、私が後に師事する小松崎茂先生が柏へ転居して来たので、私はその日から小松崎家の魅力に取り憑かれ入り浸りになってしまった。当然学業はそっちのけになり、2年生になってからは手の平を返すように成績は急降下し、担任のS先生にも、「どうしたんだ」と言って何回も職員室へ呼び出され、果ては心配の余り、自宅へも来てくれて、随分お世話を掛けた。 |
▲出版社の招待で欧州旅行中の川上宗薫(左)と菊村到
|
|
|
この辺りのことは、第一部の『小松崎茂と私』に詳述したので、ここでは省かせていただくが、各科目とも急降下した中で、宗薫先生だけはそんな私をよく理解してくれて、成績表にはかなり良い評価をつけてくれた。 宗薫先生が初めて教壇に立った日、校庭は桜が満開だった。宗薫先生は「君たちあの桜の花を見てどう感じる? オレにはけばけばしくて猥雑で正視出来ない」と言われ、変わった先生だなあと感じたのが、今も強く印象に残っている。 宗薫先生に教わったのは高校2年の一年間だけだった。独特のイントネーションで、たとえば英語を和訳する際「ナニナニのように」というのを「ナ、ナ、ノヨーニ」とか色々面白いリズムでの発音が耳に残っている。 宗薫先生との教室での交流は1年間だけだったが、宗薫先生が流行作家となり多忙をきわめるようになる直前まで、私達はかなり一緒の時間を過ごした。 | ||
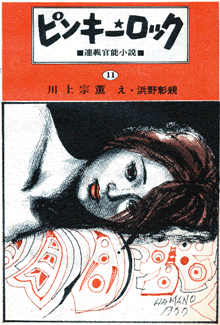
▲『週刊漫画TIMES』(芳文社)に連載された川上宗薫の『ピンキーロック』 のとびら(浜野彰親・画) |
川上宗薫と水上勉川上宗薫―芥川賞候補にノミネートされること5回―とうとう賞には手が届かなかったお人である。その後流行作家として大活躍する訳だが、ここで又一寸前号で書いた水上勉氏に筆を移すことにする。 水上勉は昭和32年9月(38歳)、文京区富坂から松戸市下矢切に転居して来た。昭和23年『フライパンの歌』を発表して以来、仕事にも恵まれず、文学への夢を抱きながらも鬱鬱(うつうつ)とした毎日を送っていた。それでもアパート、間借り生活から、松戸の一戸建ての借家に移り、若狭の実家に預けていた子供を引きとって、水上勉はやっと家庭らしきものを持つことが出来た。 文学への夢を捨てきれずに10年―水上は洋服の生地の行商で糊口(ここう)をしのいでいた。 そんなある日、水上夫人の同級生の姉と結婚していた川上宗薫が、洋服生地を分けてもらいたいと水上家を訪れた。 水上氏の前に立った川上宗薫先生はすでに芥川賞候補作家であり、水上氏があきらめかけていた文学の匂いが、その全身から漂っていた。 当時、柏や松戸には文筆業の人も少なく、柏には宗薫先生と親しい評論家の日沼倫太郎氏が居たくらいで、水上氏の噂を聞いた宗薫先生が様子を見に訪ねて行ったらしく、とに角そんなきっかけで二人の交友が始まった。 ある寒い日、宗薫先生は、菊村到(いたる)を伴い、水上家を訪れた。菊村氏は「硫黄島」で芥川賞を手にした直後だった。 |
|
|
宗薫先生の話では、その折、水上氏から手料理でもてなされたと聞いているが、菊村氏が、「あなた、小説を書いてみませんか。あんたなら書ける。期待してますよ」と励ましたそうで、この一言が、水上氏の胸に再び火をつけ、洋服の行商をやりながら、列車の中で松本清張の『点と線』をむさぼるように読んだという。 そして、半年かかって700枚の推理小説を書きあげた。その長編は書き直され河出書房から『霧と影』の書名で出版された。この水上勉のカムバック第一作は、宇野浩二の序文、吉行淳之介、菊村到の推せん文が帯についていた。 水上氏と宗薫先生は仲が良かった。しかし、水上氏は『霧と影』で華々しいカムバックをし、たちまち流行作家となった。住まいも松戸から文京区春日町の借家へ、そこから豊島区高松町に初めて家を買った。 そして宗薫先生は相変わらず『芥川賞候補作家』だった。 作家のけんか完全に立場が逆転し、その後水上氏は順調に作品を発表し、そうした事態の中で些細なことで二人の間に亀裂が入り、文壇の一部では有名な大喧嘩に発展した。 宗薫先生はこの件を『作家の喧嘩』という小説として発表(『中央公論』だったか)。激怒した水上氏は、報復として宗薫先生をモデルにした『好色』(『文芸春秋』)という作品を発表。二人の間のミゾはますます大きく深くなってしまった。 その騒ぎの真っ最中、宗薫先生の私への電話は毎日のように続いた。 学校を退職し、本格的に文筆生活に入った頃、宗薫先生は一時期上野池の端七軒町だかに仕事場を借りて通っていた。その頃は出かける前に私とお茶を飲み、時にはボヤき、(相手不足を承知で)私に文学論を吹きかけ、延々と議論を闘わせたこともあった。 水上氏の小説『好色』では宗薫先生の風貌についても、「せまい額、べっとりなでつけた髪、黒縁のメガネの奥に好色そうな眼がどうのこうの…」とかなり悪意に満ちた表現があったように記憶するが、宗薫先生は当時闘志みたいなものがむき出しで、「君、今日は目が死んでるぞ!」とよく注意された。要するに眼力(めぢから)を指してのことで、今の私の目を見たら、おそらくあきれて匙(さじ)を投げてしまうだろう、といつも思い出して反省している。 大体宗薫先生の意見と私のそれが合致することは少なく、いつも物別れが多かったが、ある時川端康成の『女であること』のヒロイン(さかえという名前だったか)の生きざまの話でめずらしく共鳴してしまい、レジで代金を払いながらの宗薫先生の忌々(いまいま)しそうな残念そうな一寸口惜しそうで意地悪そうな目つきが懐かしく思い出される。 意地悪な目付きといえば後年世田谷に新築した家には広い部屋があり、『ピンポン野球』というものを考案して興じていたというが、ある時(草野球ではちょっぴり自信があった私が)「今度挑戦に行く!」と言ったら、例の目つきで上から眺めおろし、「君なんか、かすりもしないよ。あの張本(勲)だって完敗だったんだから…」と言って、嬉しそうな笑顔にもどった。 水上氏との間の絶交は8、9年続いた。親しい佐藤愛子が直木賞を受賞した昭和44年夏、佐藤のお祝いを機に人が入って「もういいだろう」ということで和解が成立。時を経て偶然二人ともに世田谷区成城へ住むことになり、交友が復活。水上氏は、新築祝いに京都から桜の木を贈り、柏、松戸時代の親しかった昔に還った。 毎年講談社主催の『出版文化賞』のパーティが開かれるが、そのパーティに教え子である私と同席するのを宗薫先生は非常に喜んでくれた。ある年耳もとで、「おい仲直りしたぞ」と小さな声で告げてにやりと笑った。 宗薫先生のエピソードは限りない。銀座のバーで、新人ホステスの前で演じる迫真的『痴呆』の演技とか、自ら小心で、ケチで、臆病で、腕力も弱いということを広言し、ここでは披露しきれない話もゴマンとある。 ポルノ小説の大々的フロンティアといわれ、その一方で「単なるポルノ作家ではない!」と力説していた親友の菊村到氏もすでに鬼籍に入った。 宗薫先生は死の2日前まで口述筆記を続けたという。『女陰についてのみならず、迫りくる死について彼ほど饒舌に感想を語った人間は稀有である│』という山田風太郎の記述がある。 昭和60年10月13日、「もう薬も点滴もいらない。ムダなことをするな」といって、枕元の夫人にかすかに手を振ったあと昏睡状態に入り、午後10時10分永遠に「失神」した。享年61歳。葬式の喪主は、30歳の妻と、40歳の娘の二人が務めた。 (一部敬称略) |
||

